コラム

コラム
2024年12月24日
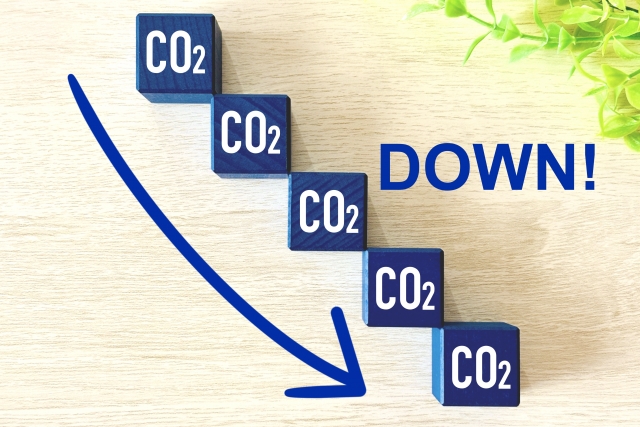
少子高齢化による労働人口の減少、パンデミックの発生、社会情勢の悪化など、様々な要因が渦巻く中で「ものづくり大国」日本の製造業はどのような状況下にあるのでしょうか。今回は日本の製造業の現状や、今後変わりゆく環境にどのような課題が発生し、どのような取り組みが必要になるのかを解説します。
目次
まず、日本の中で製造業はどのようなポジションにあるのでしょうか。
2019年の内閣府国民経済計算(GDP統計)によれば、製造業はGDP・就労人口ともに2割程度を占めており、重要な基幹産業といえます。
日本のGDPの成長率は高度経済成長期から少しずつ低下しているものの、2023年1月時点で世界3位の規模です。
また、製造業の平均賃金水準は全産業の中でも高く、特に輸送用機械、化学、電気機械などの業種がその傾向を示しています。
(1)社会情勢の変化
製造業に影響を及ぼす不確実性の要因は、新型コロナウイルス、気候変動、米中貿易摩擦、ウクライナ紛争など多岐にわたります。これらの要因が重なり合うことで原材料やエネルギーコストが高騰し、日本でも円安の影響で輸入品の価格が高騰しています。
(2)製造業のビジネスモデルの変化
かつて日本は貿易黒字が続いていた貿易立国でしたが、2022年には過去最大の貿易赤字を記録しました。国内市場の成熟化や新興国市場の成長により、国内生産基盤の維持が難しくなっています。
(3)カーボンニュートラルへの対応
パリ協定では、世界の平均気温上昇を1.5℃に抑える努力が求められており、製造業もCO2排出量の削減に努めなければなりません。エネルギー効率の向上や廃棄物の削減が求められる状況です。
(1)製品化・事業化率
日本の研究開発費は増加傾向にありますが、経営層は成果が伴わないと感じています。研究開発と経営戦略の一貫性が求められ、技術を収益化することが課題となっています。
(2)長期化しやすい開発期間
市場や顧客の課題が見えにくいため、製品化までの開発期間が3〜5年と長期化しやすいです。これにより市場競争で後れを取る可能性があります。
(3)後れを取るDX
デジタルトランスフォーメーション(DX)の欠如が問題です。材料開発や製造プロセスの迅速化が求められる時代にあって、アイデア創出や情報収集プロセスのデジタル化が進んでいません。
(4)後継者不足・技術継承の遅れ
人材不足は技術継承にも影響し、現場力が損なわれるリスクがあります。技術やノウハウをデータ化し、効率的に継承することが求められます。
(1)顧客価値と結びつけた製品・事業開発
顧客が何を求めているのか、何に価値を感じるのかを知ることが重要です。研究開発フェーズから市場を意識したアプローチが求められます。
(2)プロセスを効率化し競争力を強化する
情報収集プロセスを効率化し、適切な情報を適切なタイミングで捉えることが競争力強化の鍵です。情報視野を広げ、必要情報を効果的に活用することが求められます。
製造業は変革の最中にあり、従来の方法論や価値がすぐに陳腐化する厳しい状況です。企業が存続と成長を続けるためには、技術を顧客価値に転換し、競争力を強化する必要があります。情報収集プロセスを効率化し、適切な情報を効果的に活用することで、変化の兆しを的確に捉え、ビジネスチャンスへと転換することが重要です。
製造業の情報収集に特化したAIの力を借りて、情報精査や収集の課題を解決することを検討することも有効です。
太平洋工業(株)新規事業推進部 営業企画グループ
受付時間:営業時間内(平日9-12時、13-17時、指定休業日除く)